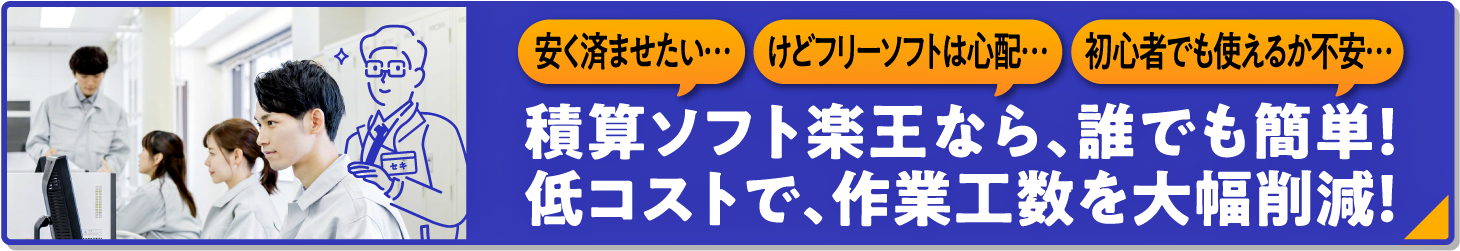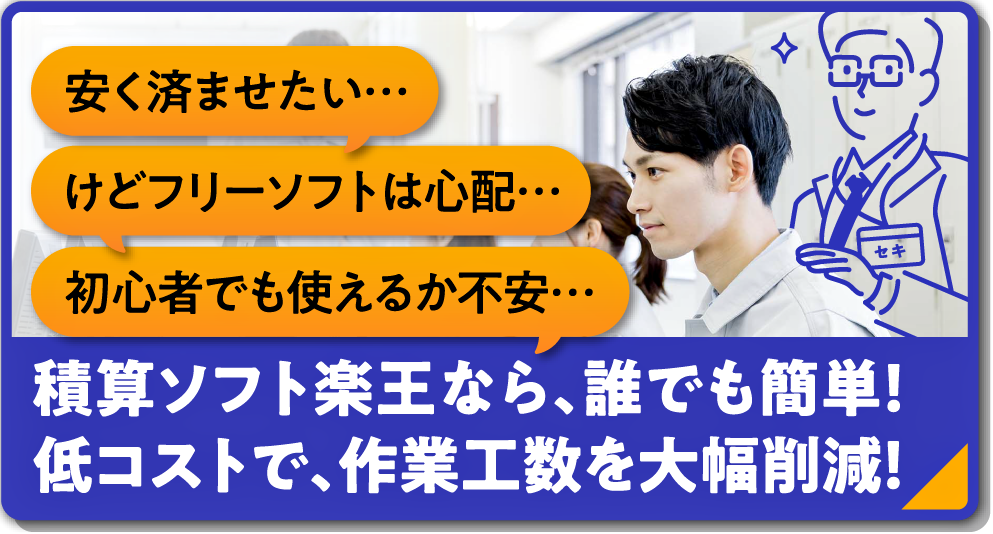こんにちは!ITの力で建設業界に貢献する「アークシステム」です。
電気主任技術者の資格には、電験三種から電験一種まで3つの資格があり、電験一種を取得すると電圧に関わらず電気設備の管理ができるようになります。
電験三種が入門と位置づけられていますが、合格率は例年10%〜15%前後と難易度が高い試験です。
今回は、電気主任技術者がどのような資格かということとあわせて、各試験の難易度や試験概要についても解説していきます。

目次
電気主任技術者とは?電験三種・二種・一種について解説
電気主任技術者とは、発電所や変電所、工場やビルの受電設備や配線など、電気設備の保安監督という仕事に従事できる資格です。
電気設備がある事業主は、設備の工事や保守、運用などをする際、保安の監督者として、電気主任技術者を専任しなければならないことが法律でも定められています。
該当する電気設備を設置する施設には必ず電気主任技術者を置かなくてはならないため、非常にニーズの高い資格といえるでしょう。
電気設備業界の動向については、こちらのコラムで詳しく解説しています。
ぜひ参考にしてみてくださいね
電験三種・電験二種・電験一種の違いは
電気主任技術者の資格には、電験三種・電験二種・電験一種の3種類ありますが、それぞれ取り扱うことができる電圧が異なります。
また、資格試験は、第三種から順に取得していかなくてはなりません。
それぞれの違いを確認していきましょう。
電験三種
電験三種は、電圧が5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5千キロワット以上の発電所を除く)の工事・保守や運用を取り扱える資格です。
電気工作物とは、電気を供給するための発電所、配送電線路をはじめ、工場、ビル、住宅の受電設備、屋内配線、電気使用設備などの総称です。
そのため、電験三種では、工場やビル、小規模な発電施設の保守や管理などが行えます。
電験二種
電験二種は、電験三種よりも取り扱える電圧が高くなり、電圧17万ボルト未満の事業用工作物の工事や保安管理が行えます。
対象となる施設は、中規模の発電施設や大規模な工場などに拡大するため、電験三種以上に専門的な知識や経験が必要です。
電験一種
電験一種を取得すると、取り扱える電圧の上限がなくなります。
大手の電力会社や発電所、変電所などを管理できるようになり、その施設の保安管理者として重要な役割を果たしていける資格といえます。
電気関連の資格には電気工事士もあります。
電気工事士の仕事内容については、こちらのコラムを参考にしてくださいね。
電気主任技術者試験の難易度と合格率

続いて電気主任技術試験の難易度や合格率を見ていきましょう。
電験三種の合格率と難易度
電験三種の受験者数や合格率は以下のようになっています。
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 令和3年度(2021年) | 37,765人 | 4,357人 | 11.5% |
| 令和4年度(2022年)上期 | 33,786人 | 2,793人 | 8.3% |
| 令和4年度(2022年)下期 | 28,785人 | 4,514人 | 15.7% |
| 令和5年度(2023年)上期 | 28,168人 | 4,683人 | 16.6% |
10〜15%前後の合格率となっていますが、10%を割ることもあり、難易度は高いといえるでしょう。
電験二種の合格率と難易度
電験二種は、一次試験と二次試験があります。
一次試験に合格した場合、二次試験が不合格になっても、翌年については二次試験から受験できる制度があります。
合格率は以下のようになっています。
| 一次試験合格率 | 二次試験合格率 | |
| 令和3年度(2021年) | 約25.7% | 約17.2% |
| 令和4年度(2022年) | 約35.2% | 約24.0% |
| 令和5年度(2023年) | 約24.5% | 約17.6% |
※一般財団法人 電気技術者試験センターを元に計算
二次試験の合格率は17%〜24%前後。
電験三種に合格している上での合格率のため、難易度は高いと考えられます。
電験一種の合格率と難易度
電験一種については、扱える電圧の上限がなくなり、仕事の幅も広がるため、資格の難易度はさらに上がります。
試験については、電験二種と同様に一次試験と二次試験があり、一次試験に合格すれば翌年は一次試験が免除となります。
合格率は以下のようになっています。
| 一次試験合格率 | 二次試験合格率 | |
| 令和3年度(2021年) | 約30.9% | 約8.0% |
| 令和4年度(2022年) | 約30.8% | 約20.9% |
| 令和5年度(2023年) | 約33.0% | 約17.9% |
※一般財団法人 電気技術者試験センターを元に計算
二次試験の合格率は20%前後ですが、一桁台の年もあります。
合格率20%台と思わず、より狭き門を突破するつもりでの勉強が必要でしょう。
電気主任技術者の試験概要もチェック

電気主任技術者の合格率や難易度を見てきましたが、試験の範囲や内容はどのようなものでしょうか?
試験概要を確認していきましょう。
電験三種の試験概要
電験三種の試験は、論理・電力・機械・法規の4科目からなり、それぞれの合格基準は60点以上(100点満点)。
しかし、試験ごとに第三種電気主任技術者試験委員会によって調整が行われる場合があります。
また、試験は、マークシートに記入する筆記方式とパソコンで解答するCBT方式が選べます。
4科目全てに合格すれば第三種電気主任技術者試験合格となりますが、1科目でも合格すれば「科目合格」となり、最大で5回まで合格した科目の試験は免除となります。
上期・下期ありますので、翌々年の試験までに4科目合格すれば、資格が取得できます。
電験二種の試験概要
電験二種は、一次試験と二次試験があります。
一次試験は第三種と同様に、論理・電力・機械・法規の4科目からなり、マークシート方式。
令和5年度(2023年)の合格基準は、90点満点中各科目とも54点以上となりました。
二次試験は、電力・管理、機械・制御の2科目で、それぞれ記述式です。
100点満点中60点以上かつ、各科目とも平均以上が合格基準(令和5年度(2023年))となっています。
電験二種試験の一次試験は、電験三種試験と同様に科目ごとの合格が認められています。
一次試験については、3年間で4科目に合格すれば二次試験の受験資格が得られ、二次試験に不合格となっても、翌年までは、一次試験が免除となります。
電験一種の試験概要
電験一種についても、一次試験は理論・電力・機械・法規の4つの科目で試験が行われます。
こちらもマークシートに記入する選択方式の試験となります。
令和5年度(2023年)試験での合格点は、各科目とも80満点中48点以上となりました。
二次試験については、電験二種同様に電力・管理、機械・制御の2科目の記述式で、令和5年度の合格基準は、100点満点換算で56.7点以上かつ、各科目とも平均点-5点以上でした。
電験二種同様に、科目ごとの合格は認められており、3年以内に4科目合格すれば良いこととなっています。
一次試験に合格すれば、二次試験で不合格となっても翌年までは一次試験が免除となります。
電気主任技術者試験の難易度は高いものの今後も資格ニーズはあり
電気主任技術者試験には、電験三種、電験二種、電験一種の3種類の試験があり、それぞれ電気主任技術者として管理できる電圧の上限が変わります。
電験一種に合格すれば、管理できる電圧の上限がなくなり、大規模な工場や大型発電所などの保守管理が可能です。
電気設備がある事業主は、電気設備の保守や運用をする際、電気主任技術者を専任しなければならないと法律で定められているため、今後もニーズのある資格といえます。
資格試験は、第三種から順に合格する必要があり、最初に取得する第三種においても、合格率は10%〜15%程度と難易度は高い資格です。
電験三種、また電験二種、電験一種の一次試験は、科目ごとの合格も認められているため、少しずつ資格の取得を目指していくことも可能です。
難易度は高いものの、その分ニーズも高い資格のため、電気工事に関わる仕事をしている方は、ぜひ挑戦してみてください。
アークシステムは、ITツールを通して、建設業に携わる方の業務をサポート。
建設業で特に手間のかかる拾い出し・積算見積をサポートする「楽王シリーズ」を提供しています。
豊富な機能をそろえ、貴社業務に合わせてオーダーメイドで製品を調整できるパッケージ版のほか、スタートしやすいサブスクリプション版も用意していますので、ニーズにあわせてご検討ください。
図面の拾い出しには、月額たったの¥3,800から使える 「ヒロイくんⅢ」もご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください!
★製品デモや資料請求はこちらから→「製品サイトお問い合わせフォーム」
★お電話でのお問い合わせはこちらから→045-451-5121045-451-5121