こんにちは!ITの力で建設業界に貢献するアークシステムです。
法定福利費とは、健康保険法、労働基準法、厚生年金保険法などの法律によって定められた「企業側の負担が義務付けられている福利厚生費」です。
つまり、福利厚生費の一部が法定福利費となります。
今回は、法定福利費に含まれる項目や計算方法、福利厚生費との違いなどについて、詳しく解説します。
現在、建設業界では見積書に法定福利費の内訳を記載するルールになっているので、その背景や算出方法についても確認していきましょう。
※本文内でご紹介するのは2025年6月時点での情報です
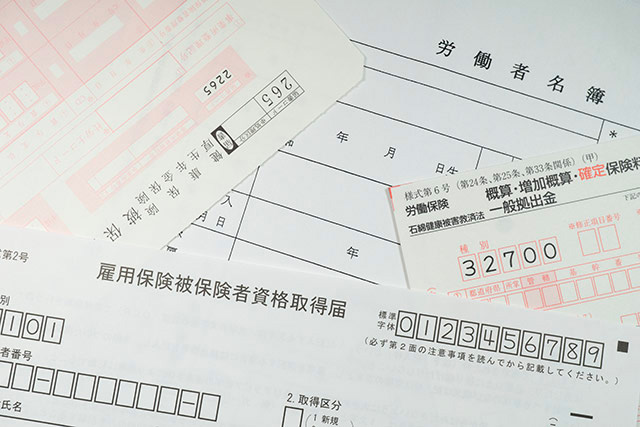
目次
法定福利費とは?福利厚生費との違いも確認
まずは、法定福利費の基本について確認していきましょう。
法定福利費とは
社員の健康維持やモチベーションアップなどを目的に、企業が給与以外に提供する費用やサービスのことを、「福利厚生」と呼びます。
この福利厚生のうち、 法律で企業側が負担を義務付けられている制度にかかる費用が「法定福利費」です。
具体的には、社会保険料や雇用保険料の企業負担分などが法定福利費に該当します。
加入要件を満たしている場合、従業員は社会保険や雇用保険に必ず加入しなければなりません。
各保険等への加入には企業にも費用負担が生じ、これが法定福利費となります。
つまり、法定福利費は、 従業員に安心して長く働いてもらうためには欠かせない費用だといえるでしょう。
福利厚生費との違い
法定福利費と福利厚生費の大きな違いは、 法律で定められている費用かどうかという点です。
前述のとおり、法定福利費は、法律で企業が負担する旨が定められた福利厚生に係る費用を指します。
一方の福利厚生費とは、法律で定められているわけではないけれど、 それぞれの企業が独自に行なっている福利厚生制度にかかる費用のことです。
福利厚生費の具体例としては、住宅手当、通勤手当、制服貸与、慶弔見舞金、社員旅行費用、歓送迎会費用などがあります。
建設業の法定福利費に含まれるものを詳しくチェック
法定福利費に含まれる項目は、以下の6つです。
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 介護保険料
- 雇用保険料
- 労災保険料
- 子ども・子育て拠出金
ここでは、法定福利費の各項目について、詳しく確認していきましょう。
1.健康保険料
健康保険は、 従業員やその家族が加入する公的医療保険です。
被保険者や被扶養者が病気やけがをしたときには、健康保険の補償により 医療費の自己負担が軽減されます。
また、休業や出産、死亡時には、各種給付金も支給されます。
【健康保険の加入対象】
健康保険の適用を受ける事業所に勤務する会社員・公務員などの正社員や、以下の条件に該当するアルバイトやパートなどの短時間労働者が加入します。
- 従業員が常時51人以上の事業所に勤務している
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である
- 継続して2カ月を超える雇用見込みがある
- 賃金が月額88,000円以上である
- 学生ではない
【健康保険保険料率】
- 協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合:都道府県ごとに異なる
- 健康保険組合の場合:各組合が独自で定める
健康保険料の具体的な金額は、標準報酬月額に保険料率を掛けて算出します。
【保険料負担割合】
従業員と企業の折半となります。
2.厚生年金保険料
厚生年金は、 老後(原則65歳以上)の老齢や障害、死亡に対して給付金をもらうための保険制度です。
基礎年金である国民年金に上乗せして支給される年金であることから、厚生年金に加入している人は、老後に受け取れる給付が手厚くなります。
【厚生年金の加入対象】
健康保険の適用を受ける事業所に勤務する会社員・公務員などの正社員や、以下の条件に該当するアルバイトやパートなどの短時間労働者が加入します。
- 従業員が常時51人以上の事業所に勤務している
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である
- 継続して2カ月を超える雇用見込みがある
- 賃金が月額88,000円以上である
- 学生ではない
【厚生年金保険料率】
2025年6月時点での厚生年金保険料率は 18.3%です。
厚生年金保険料の具体的な金額は、標準報酬月額に保険料率を掛けて算出します。
【保険料負担割合】
従業員と企業の折半となります。
3.介護保険料
介護保険は、 介護サービスを利用している人を支援するための保険制度です。
65歳以上は第1号被保険者、 40~64歳の方は第2号被保険者となり、介護保険料が発生します。
40歳から64歳までの健康保険の加入者は、健康保険料と一緒に介護保険料を納めます。
65歳以上の第1号被保険者は、お住まいの市区町村より介護保険料が徴収されます。
【介護保険の加入対象】
40歳から64歳までの健康保険の加入者です。
【介護保険料率】
- 協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合:1.59%
- 健康保険組合の場合:各組合が独自で定める
介護保険料の具体的な金額は、標準報酬月額に保険料率を掛けて算出します。
【保険料負担割合】
従業員と企業の折半となります。
4.雇用保険料
雇用保険とは、 労働者の生活の安定や就職の促進を図るための公的保険制度です。
具体的には、失業時の給付や、育児や介護などで長期休業する際の給付などを行われています。
【雇用保険の加入対象】
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である
- 31日以上継続して雇用見込みがある
【雇用保険料率・保険料負担割合】
雇用保険料の保険料率と保険料負担割合は 業種によって異なります。
2025年6月時点の雇用保険料率は以下のとおりです。
- 建設の事業:雇用保険料率1.75%(本人負担0.65%、事業主負担1.1%)
- 一般の事業:雇用保険料率1.45%(本人負担0.55%、事業主負担0.9%)
- 農林水産・清酒製造の事業:雇用保険料率1.65%(本人負担0.65%、事業主負担1.0%)
雇用保険料の具体的な金額は、賃金総額に保険料率を掛けて算出します。
5.労災保険料
労災保険とは、 労働者の仕事や通勤が原因とするケガ、病気、死亡に対する補償金を給付する保険制度で、正式名称は労働者災害補償保険料といいます。
従業員を1人でも雇っている企業は、必ず労災保険に加入しなくてはいけません。
【労災保険の加入対象】
すべての従業員が加入対象となります。
【労災保険料率】
事業の種類によって細かく分けられています。
詳細は、厚生労働省の「令和7年度の労災保険率について(労災保険率表)」をご確認ください。
労災保険料の具体的な金額は、賃金総額に保険料率を掛けて算出します。
【保険料負担割合】
企業が全額負担します。
6.子ども・子育て拠出金
国や地方自治体が子育て支援サービスを行うために、企業から徴収する費用です。
【子ども・子育て拠出金の加入対象】
従業員の子どもの有無に関係なく、厚生年金に加入している方全員 が対象となります。
【子ども・子育て拠出金率】
2025年6月時点の子ども・子育て拠出金率は 0.36%です。
子ども・子育て拠出金の具体的な金額は、標準報酬月額に保険料率を掛けて算出します。
【拠出金負担割合】
企業が全額負担します。
各種保険料率については、以下の公式Webサイト等でご確認ください。
- 健康保険料や介護保険料:協会けんぽ(または加入する保険組合)
- 厚生年金保険料や子ども・子育て拠出金率:日本年金機構
- 雇用保険料:厚生労働省「雇用保険料率について」
- 労災保険料:厚生労働省「令和7年度の労災保険率について」
ご紹介した社会保険の加入の義務についてや、未加入のリスクについてはこちらのコラムで詳しくご紹介しています。
建設業も社会保険加入は義務!加入が必要なケースや未加入のリスクも
一人親方は社会保険の加入義務はある?加入できる種類や方法を紹介
建設業における法定福利費の仕訳と見積作成

ここからは、建設業における法定福利費の仕訳と見積作成の重要性についてご説明します。
法定福利費の仕訳
会計処理では、 企業負担分の法定福利費は納付時に「法定福利費」という勘定科目で仕訳・計上します。
一方、 本人負担分については給与支払い時に「預り金」という勘定科目で仕訳・計上し、納付により「預り金」が清算されます。
給与天引きで会社が預かって会社が本人に代わって納付します。
子ども・子育て拠出金や労災保険料はその全額が企業負担のため、預り金は発生しません。
建設業の法定福利費は見積書に明示する
法定福利費は、従業員に安心して長く働いてもらうために必要な費用の一つです。
建設業での積算においては、現場作業員の法定福利費は、工事費を構成する直接工事費の 「労務費」として算出され、工事費の見積に積み上げていきます。
一方の現場以外の従業員の法定福利費については、 「一般管理費」として算出されます。
労務費や一般管理費についてはこちらのコラムもご参考ください。
建設業の積算における労務費とは?人件費との違いや計算法もチェック
積算における一般管理費とは?内訳や一般管理費等率の改定も確認!
建設業界では、2013年から「 見積書へ法定福利費の内訳を記載する」というルールが定められました。
その背景には、建設業界では下請けの零細・中小企業で社会保険や労働保険の加入義務があるにもかかわらず、 経費削減などを目的に保険に加入していない企業が存在するという問題がありました。
建設業の現場は肉体労働が多くケガのリスクも大きいため、社会保険や労働保険に加入することはとても重要です。
このような社会保険・労働保険の未加入問題を解決するためにも、見積書へ法定福利費の内訳を工事費とは別に明示するルールが定められたのです。
法定福利費を内訳明示した見積書の提出は法的な義務ではありませんが、国土交通省も「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」などで推進をしています。
見積書に明示する法定福利費の計算方法
見積書に内訳を明示するのは、 現場労働者の法定福利費が対象です。
建設工事の見積もりに明示する法定福利費の基本的な算出方法は以下になります。
◼︎法定福利費=労務費総額×それぞれの保険料率
まずは工事ごとの労務費を算出し、その労務費をもとにそれぞれの保険料率をかけて保険料ごとの法定福利費を算出します。
それをもとに、見積書には、 保険料の種類、労務費、法定福利費が分かるように明示します。
そのほか、 工事費や工事数量に平均的な法定福利費の割合をかけて法定福利費を算出する方法もあります。
◼︎法定福利費=工事費×工事費当たりの平均的な法定福利費の割合
◼︎法定福利費=工事数量×工事数量当たりの平均的な法定福利費の割合
見積書に必要な構成・項目については、「建設工事の見積書の項目は?構成や重要項目、ポイントをご紹介」でも詳しくご紹介していますので、あわせてご参考ください。
法定福利費の積算にも役立つ!「楽王シリーズ」
アークシステムでは、 拾い出し・見積作成を効率化する「楽王シリーズ」を提供しています。
計算しにくい建設業の社会保険料、つまり法定福利費も、スピーディーに正確に積算することができます。
リーズナブルな価格で導入しやすいサブスクリプション版もご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください!
■サブスクリプション版 「楽王Link」「楽王Crew」
- 【楽王Link】雛形や材料データ、見積書のオンライン共有で業務標準化!
- 【楽王Crew】担当者がお一人の企業様向け。気軽に始められる
「楽王Link/楽王Crew」は、月額制で始めやすくて続けやすく、業務の属人化、ファイル管理、業務工数の削減など、積算業務の課題をまとめて解決いたします。
まずは、気軽に始められるサブスク版で始めましょう!
製品サイトより、ぜひお申込みください!
■パッケージ版 「楽王3」
- 【楽王3】業務課題をヒアリングし、まとめて解決可能!組織運用に乗せる充実のサポートが可能な旗艦モデル
- 自社独自の積算ルールを変えずに、業務をより効率化したい…
- 初めての積算見積ソフトの導入で、サポートを受けながら利用したい…
- いろいろな業者に問い合わせたけど、自社の要件に合った積算見積ソフトが見つからない…
そのような企業様には、「楽王3」がおすすめ!
貴社独自の計算方法や、材料、単価、帳票の雛形など、業務でのご要件に合わせてカスタマイズし、貴社の業務にベストマッチするソフトを納品。
貴社の業務課題をヒアリングし、まとめて解決できる積算ソフトです。
また、運用に乗る充実のサポート体制も魅力。
業務負担をかけないスケジュールを提示し、しっかり寄り添いサポートいたします。
まずは製品サイトより、お気軽にご要件をお聞かせください!
■サブスク/パッケージ版 拾い出しソフト「ヒロイくんⅢ」
積算に必要な「拾い出し」の際には、読み込んだPDFやCAD図面を マウスクリックだけで拾い出せる「ヒロイくんⅢ」もあわせて導入をご検討ください。
誰でも簡単に使えるシンプルさが魅力の製品です。
積算・拾い担当者だけでなく、営業担当者様や職人さんも利用する企業様もいらっしゃいます!
資材の数量や長さ、面積、体積などを簡単操作で拾い出し可能で、自動計算と自動集計により、工数削減はもちろんヒューマンエラーの防止にも寄与します。
拾い出した結果を楽王に取り込むことで、見積内訳を自動作成。
製品デモを実施中!
資料請求やデモ依頼は製品サイトより、ぜひお気軽にお申込みください。
建設業の法定福利費とは法律で義務付けられた福利厚生にかかる費用!
法定福利費とは、 企業が従業員に提供する福利厚生の中で、法律で義務付けられているものにかかる費用です。
具体的には、 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料、子ども・子育て拠出金の企業負担分が該当します。
企業や従業員が加入要件に該当する場合には、これらの保険や拠出金に必ず加入しなければなりません。
建設業界では、長く 健康保険や雇用保険の未加入問題があり、それを解決するためにも2013年から見積書へ、工事費とは別に法定福利費の内訳を明示することがルール化されました。
法定福利費の内訳を明示することで、工事費ごとの請負金額の中で法定福利費を確保しやすくすることを目的としています。
建設業の会計処理にあたっては、 法定福利費もしっかりと積算・見積に反映させ、適正な価格での工事受注を目指しましょう。
アークシステムでは、建設業向け拾い出し・積算見積ソフト「楽王シリーズ」をご提供しています。
積算見積業務の効率化の第一歩として、ぜひ積算見積ソフトの導入も検討してみてくださいね。
★製品デモや資料請求はこちらから⇒「製品サイトお問い合わせフォーム」
★お電話でのお問い合わせはこちらから→045-451-5121045-451-5121











