こんにちは!ITの力で建設業界に貢献するアークシステムです。
工事にかかる費用を一つひとつ積み上げて工事費を算出する積算は、高度な専門知識が必要な業務。
この積算業務に関しては、建築コスト管理士という資格があり、資格取得者は積算を用いたコスト管理のスペシャリストとして活躍しています。
では、建築コスト管理士資格はどんな資格でどんな知識が必要とされるのでしょうか。
また、資格試験の難易度はどれくらいなのでしょうか。
今回は、「建築コスト管理士」の資格について、概要から試験難易度、試験対策まで詳しく解説します。

目次
積算に携わるなら建築コスト管理士の資格がおすすめ!どんな資格?
建築コスト管理士とは、 建設業の積算におけるスペシャリストであることを認定する資格です。
公益法人 日本建築積算協会により認定されています。
積算とは、建築工事の工事費を算出する専門業務のこと。
建築コスト管理士は、積算に関する知識はもちろん、コスト情報収集・分析、発注戦略、建築関連法規など広い分野における専門知識が必要とされる専門性の高い資格で、建設業界で重宝されています。
建設業の積算については、「積算とは?その仕事内容や向いているタイプ、仕事の探し方までご紹介」で詳しく解説しています。
建築コスト管理士の仕事内容は?
建築コスト管理士は、 建築に関するコスト管理全般を担う専門家です。
建設工事の予算策定から工事終了までの全過程において、コストマネジメントを行います。
機能や性能に見合ったコストを見極め、信頼性や透明性、適切性などを管理し、発注者や設計者へ提案やアドバイスをすることもあり、コストの最適化という面でも重要な役割を果たします。
建築コスト管理士は、 建設会社や設計事務所、不動産デベロッパー、公共機関など、建設に関わるさまざまな会社で活躍しています。
また、工事品質を維持しながらコストを削減する提案(VE提案)を行うことも、建築コスト管理士が関わる重要な仕事の一つです。
VE提案については、「建設におけるVE提案を解説!導入効果や資格、事例までを詳しく」でご説明しています。
建築コスト管理士資格取得のメリットは?
建築コスト管理士資格の取得には、以下のメリットが期待できます。
- 信頼性が高まる
- 就職や転職に有利
- 収入アップが狙える
建築コスト管理士の資格を取得することで、専門性の高い知識・技術を有することを証明でき、 就職や転職が有利になる可能性があります。
また、資格取得によって 収入が上がったり昇進したりといったチャンスも生まれます。
フリーランスとして働く場合であれば、 知識・技術への信頼性の高さから、より条件の良い契約ができる可能性も高くなるでしょう。
建築コスト管理士と建築積算士との違いは?
積算の専門知識があることを証明する資格には、建築コスト管理士以外にも、「 建築積算士」という資格があります。
建築積算士は、公益社団法人日本建築積算協会が認定する資格で、建築コスト管理士の下位資格にあたります。
これらは、どちらも建設工事の工事費算定に関するスペシャリストであることを証明する資格であることに違いはありません。
しかし、 建築積算士の担う業務は特定工事の算定が中心であり、総合的なコストマネジメントを行う建築コスト管理士と比較すると、その内容は限定的となります。
建築積算士の資格についてはこちらのコラムでも詳しくご紹介しています。
建築積算士の資格について解説!難易度や試験内容、取得のメリットとは
建築コスト管理士資格の難易度は?試験概要も詳しくチェック
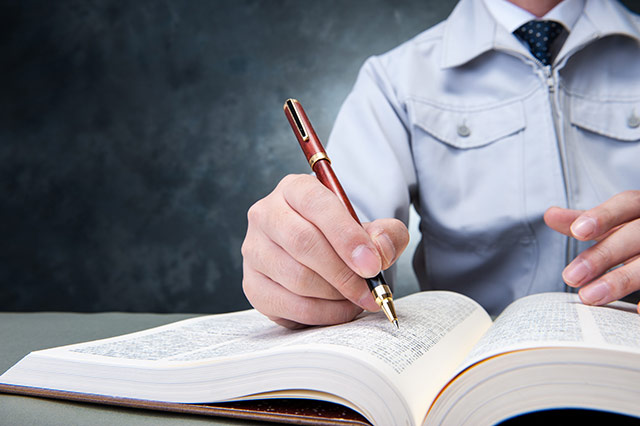
建築コスト管理士の資格認定を受けるためには、公益社団法人 日本建築積算協会が実施している資格試験に合格する必要があります。
ここでは、その試験内容と難易度について確認していきましょう。
建築コスト管理士の試験概要
公益社団法人 日本建築積算協会による2025年度「建築コスト管理士」試験案内によると、建築コスト管理士の試験概要は、以下のとおりです。
※試験概要は2025年6月時点のものです。
【実施時期】
年に1回、毎年度10月下旬頃
【受験資格】
下記のうちいずれかの条件を満たすこと
- 建築積算士の称号を取得後、更新登録を1回以上行なった方
- 建築関連業務(※)を5年以上経験した方
- 一級建築士に合格し登録した方
※建築関連業務には、建築士法で定められた、大学院修了課程の期間を算入することができます。
【試験地】
札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、鹿児島、沖縄
【受験費用】
29,700円
※過去2年内に学科試験に合格し、短文記述試験のみ受験する場合は16,500円
また、建築コスト管理士試験合格後、資格登録手数料に15,400円(税込)がかかります。
【試験方法】
- 学科試験(2時間30分、4肢択一問題、60問)
- 短文記述試験(2時間、200字以内の記述問題、5問)
【合格基準】
60%が目安
※年度による変動あり
資格登録の 有効期間は5年間で、有効期間内に CPD(継続能力開発)制度の必要単位数を取得することで登録更新が可能です。
なお、建築コスト管理士資格は、 日本建築積算協会の個人正会員であることが資格登録条件となります。
会員でない方については、試験合格後の登録と同時に、個人正会員入会申込みが必要です。
建築コスト管理士試験の合格率と難易度は?
建築コスト管理士試験の近年の合格率は以下のとおりです。
- 2024年:合格率40.7%(合格者146人/受験者359人)
- 2023年:合格率54.8%(合格者160人/受験者292人)
- 2022年:合格率47.9%(合格者138人/受験者288人)
- 2021年:合格率63.3%(合格者140人/受験者221人)
- 2020年:合格率67.0%(合格者122人/受験者182人)
近年の 合格率は40〜60%台を推移しています。
合格率には幅があるものの、試験の難易度は著しく高いということはありません。
しっかりと勉強すれば、合格を目指せる資格です。
建築コスト管理士資格試験に合格するための対策と勉強法
ここからは、建築コスト管理士の資格試験に合格するための対策や勉強法についてご紹介します。
ガイドブックをチェックする
建築コスト管理士資格試験については、公益社団法人 日本建築積算協会が 参考図書として『新☆建築コスト管理士ガイドブック』を挙げています。
試験への合格を目指すには、このガイドブックをよく確認し、内容を理解しておくことが重要です。
ガイドブックの内容は随時改訂されているので、その点にも注意しましょう。
過去問を解く
過去問は、必ず数年分を解き、その内容を分析しておくようにしましょう。
過去問について理解を深めておけば、 出題傾向を掴むとともに、 自分の苦手分野を把握することができます。
記述問題については、 指定の文字数内・時間内で問題を解けるよう練習を重ねておきましょう。
実務をイメージしながら学習する
建築コスト管理士の資格試験の内容は、実務に即したものとなっています。
日常的に実際に行なっている業務を学習内容に紐付けながら学習すれば、テキストや問題の内容を理解しやすくなります。
建築コスト管理士資格の難易度や試験内容をチェックして挑戦しよう!
建築コスト管理士とは、 建築のライフサイクル全般でコストマネジメントに携わるスペシャリストであることを証明する資格です。
プロジェクトの企画から工事の終了まで、総合的なコスト管理や最適化を担います。
建築コスト管理士の資格試験は、 建築積算士資格取得者や建築関連業務の経験者などが受験可能で、近年の 合格率は40~60%程度。
難易度が高すぎるというわけではなく、しっかりと必要な対策を取ることで資格取得を目指すことができるでしょう。
合格後は、 日本建築積算協会への会員登録と建築コスト管理士資格の登録が必要です。
資格合格を目指すなら、ガイドブックや過去問をしっかり理解することが大切。
内容を実務に紐づけて考えれば、より理解は深まるでしょう。
月額¥3,800-から始められる!積算ソフト「楽王シリーズ」
アークシステムは、ITツールを通して、建設業に携わる方の業務をサポート。
建設業で特に手間のかかる 拾い出し・見積作成をサポートする「楽王シリーズ」を提供しています。
月額¥3,800!クリックだけで拾い出し。「ヒロイくんⅢ」
図面の拾い出しには、 月額たったの¥3,800(税込)から使える 「ヒロイくんⅢ」をご用意しています。
読み込んだ図面をマウスでクリックするだけの簡単操作で、初心者にも簡単に拾い作業ができる製品です。
難しい拾い出し業務がシンプルに。手作業から約50%もの工数を削減 ※当社調べ
安価な月額制で始めやすくて、続けやすいヒロイくんを是非お試しください!
月額制で始めやすく、続けやすい。「楽王Link/Crew」
拾い出し後の見積作成には、「楽王」が活躍します!
単価データには全日出版社の 「積算実務マニュアル」の情報を収録。民間/公共工事の両方に対応し、単価を切り替えて積算が可能です。
検索機能により目的の材料がスムーズに見つかるため、 単価の確認にも活躍します。
コストを抑えて自社仕様にフィット。「楽王3」
「フルオーダーなら理想の仕様にできるけれど、コストが合わない…」
「たくさん見積ソフトがあるけれど、自社に合うものがわからない…」
「積算ルールがバラバラで、運用の整理もしたい…」
そんなお悩みに応えるのが、 セミオーダー型積算ソフト「楽王3」。
フルオーダー開発のような 高額コストをかけずに、自社に最適な環境を構築できます。
また、貴社の運用を丁寧にヒアリングし、最適なカスタマイズと運用方法をご提案。
ソフトの導入を機に、 業務の見直しや整理を進めたい企業様にも最適です。
まずは、どんなお悩みもご相談ください!
★製品デモや資料請求はこちらから→「製品サイトお問い合わせフォーム」
★お電話でのお問い合わせはこちらから→045-451-5121045-451-5121











