こんにちは!ITの力で建設業界に貢献する「アークシステム」です。
近年、大規模災害や感染症拡大といった予期せぬ事態が相次ぐ中、建設業界でもBCP(事業継続計画)対策への注目が集まっています。
建設業は社会基盤の整備・復旧という使命を背負っているため、緊急時においても業務を維持し、地域再生に力を注ぐことが期待されています。
とはいえ、BCP対策について「どこから手をつければ良いのか」「どんな内容を組み込むべきなのか」と対応に悩む建設事業者の方は少なくないでしょう。
そこで今回は、建設業でのBCP対策の基礎知識から実際の策定手順まで丁寧に説明します。
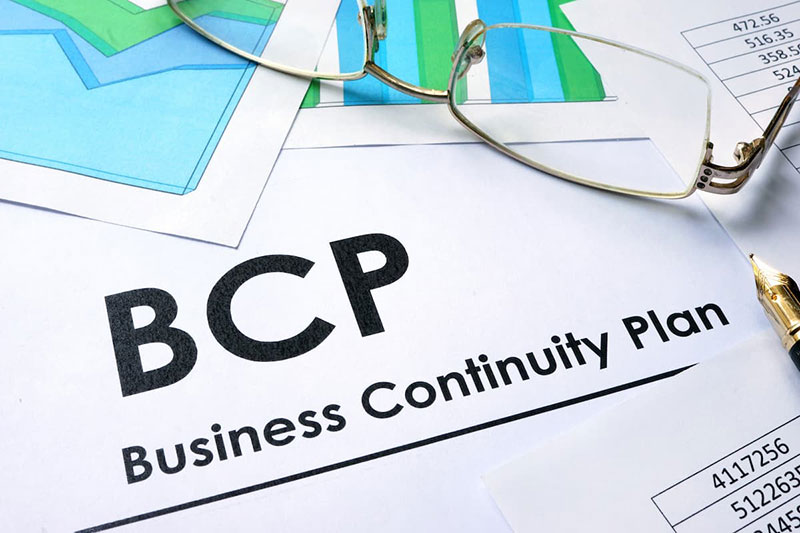
目次
そもそも「BCP対策」とは?
BCP(Business Continuity Plan)は、事業継続計画と呼ばれる仕組みです。
大規模災害や感染症の流行といった緊急事態に見舞われても企業が主要業務を止めることなく、もし一時停止した場合でも、目標期間内に業務を回復できるよう準備する計画を指します。
従来の災害マニュアルとは性質が異なり、事業の持続と迅速な回復に重点を置いた、より戦略的で幅広い計画と位置付けられるでしょう。
建設会社は、たとえ災害や事故による被害を受けても、主要業務の維持や、停止した際もなるべく短期間での再開が期待されます。
このニーズに応えるべく事業維持を目指す計画がBCPであり、今日の企業運営で欠くことのできない要素となっています。
建設業でもBCP対策が重要!
建設業界でのBCP対策は、他分野と比べても特に重要性が高いと考えられています。
その背景と現在の状況について詳しく見ていきましょう。
建設業でのBCP対策の現状
内閣府のデータによると、2023年度(令和5年度)における建設業のBCP策定率は63.4%。
この数字は他業種と比較すると3番目とやや高いですが、まだ十分なレベルに到達していないのが実情です。
策定が思うように進まない主な理由として、策定に必要な専門知識や技術の不足、人材や時間の確保が困難、策定にかかる費用や効果が見えにくいことなどが指摘されています。
さらに、建設業は現場作業が中心で、在宅勤務やデジタル化などのIT活用、つまり業務効率化が遅れていることも、策定の妨げとなっている可能性があります。
建設業の業務効率化については、以下もぜひお読みください。
建設業で業務効率化を進めよう。効率化が必要な理由や方法を詳しく!
建設業でBCP対策が必要とされる理由
建設業でBCP対策が特に重要視される理由は、以下の通りです。
社会基盤の維持・復旧における責任
建設業は、緊急時に社会基盤の復旧や応急住宅の建設など、社会的な役割を担う業種です。
土砂除去や道路の応急修理といった道路復旧作業、ライフライン修復など、緊急時には地域を支える存在としての使命が求められています。
業務の中断や遅れは、被災者や地域社会に深刻な影響をもたらすため、安定した事業運営が不可欠です。
事業の特色による必要性
建設業には、一つの建設会社だけでは全ての工事を完結できないという特色があります。
これは、元請けであるゼネコンが、専門工事業者である下請け・孫請けの会社に工事を委託する多重下請け構造で成り立っていることが理由の一つです。
中小規模の事業者は、基礎工事や電気設備工事、内装工事などの特定の工事に特化した専門技術や労働力、機材を持っています。
災害が発生し、ゼネコンがBCPを策定していても、下請けの中小事業者が被災し事業を継続できなければ、現場の労働力や資機材が途絶えてしまいます。
緊急時に人材や資材を最大限に活用するには、中小規模の事業者にもBCP普及を広げていくことが必要です。
対策しない場合のリスク
BCP対策を実施しない場合、以下のようなリスクが想定されます。
経営への打撃
人手に依存する建設業は、自然災害などの予期せぬ事態による損害に対して弱い傾向があります。
損害の程度によっては事業を廃止せざるを得ないケースも珍しくはありません。
BCP対策を十分に行なっていないと、そのリスクは大きくなります。
社会的評価の低下
緊急時に適切な対応ができない場合、顧客や地域からの信頼を失う恐れがあります。
また、復旧支援に参加できないことで、企業の社会的使命を果たせないと見なされるリスクもあります。
競争上の不利
BCPを策定していない企業は、BCP対策をしている同業他社と比べて、受注機会の減少や金融機関からのマイナス評価などといったリスクを負う可能性があります。
建設業でのBCP対策の流れ

建設業がBCPを策定する際の具体的な手順を説明します。
①目的と体制を明確にする
まず、BCP策定の目的(従業員の安全確保、事業継続、社会貢献など)を明確にします。
可能であればBCPに関する責任者を配置し、全社的に取り組む体制を整えましょう。
この段階で、災害時でも維持すべき「核となる事業」を特定することも重要です。
②リスクと影響を洗い出す
自社の事業所や工事現場がどのような災害リスクに直面する可能性があるかを洗い出し、それらが事業に与える影響(設備損壊、サプライチェーンの途絶、従業員の負傷など)を具体的に検討します。
特に、建設業は現場が分散しているケースが多いため、現場ごとのリスク評価も大切です。
連絡拠点もエリアごとに分けて設けると安心につながります。
③事前に対策を行う
リスクと影響の洗い出しが終わったら、それらを軽減するための事前対策を講じます。
例えば、次のような対策が考えられます。
人材・資機材の確保
他社との応援協定、代替の資材調達ルートの確保、非常用発電機や重機燃料などの備蓄を行います。
特に、事前に他社との協力関係を築いておくことが大切です。
建設工事では、鋼材や木材などの資材や、重機や足場などの機材の確保が欠かせません。
他社からの提供があってこそ、事業を継続できることもあります。
各拠点が同業他社と協力関係を築いておけば、被害の少ない会社から応援を得られやすくなり、人員や資材・機材の確保につながります。
情報・データの保全
緊急時に情報システムが確実に復旧できるように、バックアップ体制を整備しておく必要があります。
施工管理の情報や図面、機密情報などのデータを適切に管理しておけば、破損や消失などを免れ、スムーズに事業を再開させられます。
バックアップの手段としては、クラウドサービスの利用が注目されています。
クラウドサービスは、場所を問わず業務を進められ、セキュリティレベルが高く、バックアップデータの安全性が確保できるため、BCP対策に向いています。
アークシステムのクラウド型積算見積ソフト「楽王Crew・楽王Link」は、複数拠点でのリモートワークやBCPにも対応!
見積データやマスタなどのファイル共有機能で組織の業務標準化も実現できます。
建設業では、BCP対策に役立つクラウドサービスが、利用しやすいサブスクリプション形式で多数販売されています。
以下でもご紹介していますので、あわせてご覧ください。
建設業で活用できるサブスクサービスとは?活用して業務効率化を
④緊急時の体制とルールを定める
災害発生時に従業員が何をすべきか迷わないように、具体的な行動指針を定めます。
例えば、以下のようなポイントです。
指揮命令系統
緊急事態に対応するための対策本部を設置し、指揮命令系統を明らかにしておくことが重要です。
責任者や各グループのリーダーなどの重要人物が緊急時に不在や連絡が取れなくても、指揮・命令が滞らないよう、代理者を複数準備し、その代理順位を決めておきます。
現場対応/竣工物件への対応
施工中の物件では、速やかに重機の稼働を停止し、現場と周辺の安全確認を行うといった具体的な行動ルールを定めます。
これは、現場や周囲の二次災害を避けるためにも必要な対応です。
災害発生後に周囲に危険が及ぶリスクがあるようなら、行政と連携しながら、関係者や周辺住民への説明や避難要請をサポートする役割を担うこともあります。
これらの対応についても、BCPの中で明確化しておきましょう。
また、建設会社は、竣工物件にも管理責任を持ちます。
災害発生時には、竣工物件の状況確認や発注者のサポートを行う必要があるため、この点についてもBCPに示す必要があります。
インフラ復旧への迅速な対応
建設会社は、緊急時に要請される可能性が高い復旧工事を予測するとともに、その復旧に必要な人員や資源などについても把握しておくことが必要があります。
また、救援・復旧作業にあたれるような他社との協力体制を整えておくことも重要です。
⑤定期的な訓練と見直し
策定したBCPがきちんと運用できるよう、定期的に訓練(避難訓練、安否確認訓練、災害対策本部設置訓練など)を実施し、計画の実効性を高めます。
訓練で得られた課題や、新たなリスク情報を踏まえて、定期的にBCPを更新していきましょう。
建設業のBCP対策を整備し事業継続と社会貢献を両立して
建設業でのBCP対策は、自社の事業継続だけでなく、社会全体の早期復興にも大きく寄与する重要な取り組みです。
緊急時に社会基盤の復旧や応急住宅の建設など、地域を支える存在として期待される建設業にとって、計画の策定は社会的使命でもあります。
BCP策定には、段階的な手順を踏む必要があります。
まずは目的と体制を明確にし、災害リスクとその影響を洗い出すことから。
それをもとに事前対策を行い、緊急時の具体的な体制とルールを定めていきます。
BCP策定後には、定期的な訓練や見直し・更新も忘れずに行なっていきましょう。
建設業のBCP対策は、会社と社会のために重要です。
万が一の災害時に、経営への打撃を減らし、企業価値を発揮するためにも、BCP対策の整備に力を入れましょう。
月額¥3,800-から始められる!積算ソフト「楽王シリーズ」
アークシステムは、ITツールを通して、建設業に携わる方の業務をサポート。
建設業で特に手間のかかる拾い出し・見積作成をサポートする「楽王シリーズ」を提供しています。
月額¥3,800!クリックだけで拾い出し。「ヒロイくんⅢ」
図面の拾い出しには、月額たったの¥3,800(税込)から使える「ヒロイくんⅢ」。
読み込んだ図面をクリックするだけの簡単操作で、簡単に拾い作業ができる製品です。
難しい拾い出し業務がシンプルに。手作業から約50%もの工数を削減 ※当社調べ
安価な月額制で始めやすくて、続けやすいヒロイくんを是非お試しください!
月額制で始めやすく、続けやすい。「楽王Link/Crew」
拾い出し後の見積作成には、「楽王」が活躍!
単価データには全日出版社の「積算実務マニュアル」の情報を収録。
民間/公共工事の両方に対応し、切り替えて積算が可能です。
検索機能により目的の材料がスムーズに見つかるため、単価の確認にも活躍します。
コストを抑えて自社仕様にフィット。「楽王3」
「フルオーダーなら理想の仕様にできるけれど、コストが合わない…」
「たくさん見積ソフトがあるけれど、自社に合うものがわからない…」
「積算ルールがバラバラで、運用の整理もしたい…」
そんなお悩みに応えるのが、セミオーダー型積算ソフト「楽王3」。
フルオーダーのような高額なコストをかけずに、自社に最適な環境を構築できます。
貴社の運用を丁寧にヒアリングし、最適なカスタマイズと運用方法をご提案します。
ソフトの導入を機に、 業務の見直しや整理を進めたい企業様にも最適です。
まずは、どんなお悩みもご相談ください!
★製品デモや資料請求はこちらから→「製品サイトお問い合わせフォーム」
★お電話でのお問い合わせはこちらから→045-451-5121045-451-5121











