こんにちは!ITの力で建設業界に貢献する「アークシステム」です。
「足場図面の書き方がわからない」「どこから手をつけて良いかわからない」とお悩みではありませんか?
足場図面は安全な作業環境を確保するために欠かせない重要な設計図であり、正確に作成できなければ現場での安全性に大きな影響を与えてしまいます。
そこで今回は、足場図面の基本的な書き方について、足場の種類から具体的な作成手順まで詳しく解説します。

目次
足場にはどのような種類がある?
足場図面を作成する前に、まずは足場の種類について知っておきましょう。
足場にはいくつかの種類があるため、それぞれの足場の特徴を理解しておくことが大切です。
代表的な足場の種類
現場の条件や作業内容に応じて適切な足場を選択することが、安全で効率的な工事につながります。
代表的な足場の種類と特徴を紹介します。
単管足場の特徴
単管足場は、 直径48.6mmの鉄製パイプ(単管)をクランプという金具で接続して組み立てる足場です。
最大の特徴は、 狭い場所でも設置できる柔軟性があることです。
単管をクランプで自由に接続できるため、複雑な形状の建物や限られたスペースでも対応できます。
ただし、他の足場と比較すると 強度や安全面では劣るため、 低層建物での使用に適しています。
組み立てや解体に時間がかかることも考慮しておく必要があるでしょう。
くさび式足場の特徴
くさび式足場は、正式にはくさび緊結式足場と呼ばれる足場です。
建設現場ではくさび式足場を「 ビケ足場」と呼ぶことも多いですが、ビケ足場は厳密にはくさび式足場の認定を受けた部材とは規格が違います。
くさび式足場は、 部材にあらかじめ設けられたコマ(くさびを差し込む穴)に、くさび付きの部材を差し込んで組み立てる足場です。
組み立てにはハンマー1本があれば十分で、 作業効率が非常に高いのが特徴です。
強度と耐久性に優れており、 高さ31mまでの足場組立が可能です。
単管足場に比べて設置スペースが必要になりますが、安全性と作業性のバランスが取れた足場といえるでしょう。
枠組み足場の特徴
枠組み足場は、 工場で製造された定型の建枠を使用して組み立てる足場です。
工場生産された部材を使用するため、品質が安定しており、 高い強度と安全性を確保できます。
組み立て作業も比較的簡単で、大規模な建設現場でよく採用されています。
高さ45mまでの施工が可能で、重量物を扱う作業にも対応できます。
ただし、部材が大きいため、 設置や搬入には十分なスペースが必要です。
現場に適した足場の選び方
適切な足場を選択するには、以下のポイントを総合的に判断することが大切です。
- 建物の高さと規模
- 設置スペース
- 作業期間
例えば、ご紹介した通り足場によって 対応できる高さが異なるため、低層建物なら単管足場、中高層なら枠組み足場やくさび式足場…など、現場の建物の高さに応じてどの足場を選ぶかを考える必要があります。
また、狭い現場では単管足場、十分なスペースがあるのであれば枠組み足場を検討するなど、 設置スペースも考慮して選びましょう。
作業期間についても確認し、短期間なら組み立てが簡単なくさび式足場、長期間なら安定性の高い枠組み足場などがおすすめです。
仮設材については「仮設材(仮設資材)とは?種類や使われる工事について解説」でも詳しく解説しています。
あわせて参考にしてください。
足場図面の基本の書き方
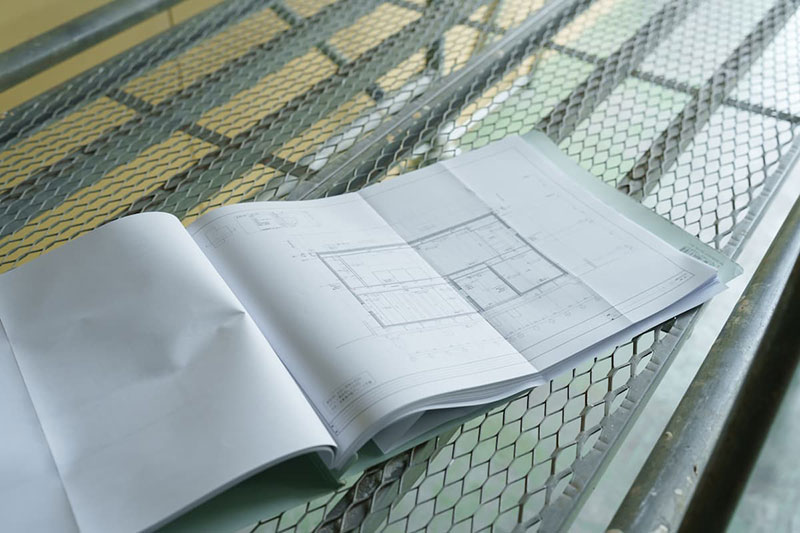
足場図面とは、 建物を建設、補修などをする場合に外周部に設置する足場の設置位置を明確に示した図面を指します。
足場の種類、配置位置、高さ、使用する部材などが詳細に記載されており、現場作業員が安全に、そして効率的に足場を組み立てるための重要な指針となります。
足場図面には平面図、立面図、部分詳細図などがあり、それぞれが異なる視点から足場の情報を示します。
足場図面の基本の書き方
足場図面の作成は、 現場の安全性と作業効率を左右する重要な作業です。
ここでは、基本の作成手順を詳しく解説します。
1.現地調査
足場図面を作成する前には、必ず 現地調査を行います。
新築工事の場合でも、図面と実際の現場状況が異なる場合があります。
既存建物の場合は、図面が存在しなかったり、図面と現況に相違があったりすることも少なくありません。
2.建物の寸法確認
建物の外形寸法を正確に測定し、足場設置に必要な情報を収集します。
壁の厚み、軒の出、出窓などの 突出部分も忘れずに確認しましょう。
これらの情報は、 足場と建物の適切な離隔距離を決定するために必要です。
3.敷地境界と干渉物のチェック
敷地境界線を越えて足場を設置することは法的に問題となるため、 境界線の位置を正確に把握する必要があります。
また、エアコンの室外機、配管、既存の構造物など、 足場設置に影響する干渉物の有無と位置も詳細に調査します。
これらの情報は、足場の配置計画を立てる際の重要な判断材料となります。
4.建築物の図面作成
現地調査で得た情報をもとに、 建築物の平面図と立面図を作成します。
新築の場合は既存の設計図面を活用できますが、 改修工事などでは実測に基づいて図面を作成する必要があります。
平面図では建物を上から見た形状と寸法を、立面図では側面から見た高さと形状を表現します。
足場の配置計画には平面図を、 高さ関係の検討には立面図を主に使用します。
両方の図面を併用することで、三次元的な足場配置を正確に計画することができます。
平面図と立面図については、こちらもコラムもご参考ください。
立面図とは?作成するときのポイントや他の図面との違いもご紹介!
5.必要な寸法情報の整理
図面には、 足場設置に必要な寸法情報を漏れなく記載します。
建物の外周寸法、各部の高さ、開口部の位置とサイズなどを明確に示すことで、後の作業がスムーズに進められます。
6.足場の平面的な配置計画
建築物の情報が整理できたら、 足場の平面的な配置を計画します。
安全性と作業性を両立させるため、適切な配置ルールに従って計画を進めることが重要です。
特に、次のルールには注意して計画しましょう。
【壁離れ300mmの基本ルール】
足場と建物外壁の間隔は、基本的に 300mm程度を確保するのが一般的です。
この距離は作業性と安全性のバランスを考慮して設定されており、現場での暗黙のルールとして広く採用されています。
ただし、作業内容や建物の形状によっては、250mm~350mm程度の範囲で調整することもあります。
【足場板の割り付けルール】
足場板の標準寸法(幅600mm、長さ1800mm)を基準として、建物周囲に効率良く配置します。
建物の角や端部では寸法が合わない場合があるため、短い足場板を使用して調整します。
メーター規格では1800mm、1500mm、1200mm、900mmの順に、300mmずつ短くなる部材を組み合わせて使用するのが一般的です。
7.高さ関係の設定
平面的な配置が決まったら、次は 高さ方向の計画を立てます。
作業内容と建物の形状に応じて、適切な作業床の高さを設定することが重要です。
作業床の高さ決定には グランドレベル(GL)と呼ばれる地盤面の基準高さを使用します。
現場の地盤が平坦でない場合は、最も高い部分を基準として設定します。
低い部分を基準にすると、根がらみ(足場の安定化部材)が適切に設置できなくなる可能性があるためです。
8.建物との干渉確認
窓や軒の出、玄関などとの干渉を事前にチェックし、 必要に応じて足場の高さや配置を調整します。
特に玄関部分では、 人の出入りに支障をきたさないよう十分な配慮が必要です。
作業床の位置を調整したり、一時的に取り外し可能な構造にしたりする工夫も検討しましょう。
9.符号・設備の記入
計画が固まったら、実際に図面に記入します。
正確で分かりやすい図面にするため、統一されたルールに従って記載することが大切です。
【寸法と符号の記載】
足場図面には、 各部材の種類や寸法を示す記号(符号)を記載します。
寸法線には実際の数値を mm単位で記載し、誤解を招かないよう明確に表示します。
部材の接続方法や特別な注意事項がある場合は、注記として追加することも重要です。
【安全設備の表示】
手すり、中桟、巾木、階段などの 安全設備の配置も図面に明記します。
これらの安全設備は法的に設置が義務付けられている場合が多いため、適切な位置と数量を確保する必要があります。
特に階段の位置は作業動線に大きく影響するため、効率性と安全性の両面から検討しましょう。
なお、足場作業については「足場作業に必要な資格とは?種類と取得方法を解説」でも詳しく解説しています。
あわせて参考にしてくださいね。
足場図面の書き方をマスターして安全な現場作業を実現
足場図面は、 建物を建設、補修などをする場合に外周部に設置する足場の設置位置を示したものです。
現場作業を安全に・効率的に進めるために重要な役割を担う図面の一つでもあります。
単管足場、 くさび式足場、 枠組み足場などの特徴を理解し、現場に適した足場を選択しましょう。
図面作成は、現地調査による正確な情報収集から始めます。
建物との適切な離隔距離の確保、足場板の効率的な割り付け、安全設備の適切な配置まで、段階的に計画を進めることが重要です。
正確でわかりやすい図面を作成することで、 施工品質の向上と事故の防止につながります。
月額¥3,800-から始められる!積算ソフト「楽王シリーズ」
アークシステムは、ITツールを通して、建設業に携わる方の業務をサポート。
建設業で特に手間のかかる拾い出し・見積作成をサポートする「楽王シリーズ」を提供しています。
月額¥3,800!クリックだけで拾い出し。「ヒロイくんⅢ」
図面の拾い出しには、月額たったの¥3,800(税込)から使える 「ヒロイくんⅢ」。
読み込んだ図面をクリックするだけの簡単操作で、簡単に拾い作業ができる製品です。
難しい拾い出し業務がシンプルに。手作業から約50%もの工数を削減 ※当社調べ
安価な月額制で始めやすくて、続けやすいヒロイくんを是非お試しください!
月額制で始めやすく、続けやすい。「楽王Link/Crew」
拾い出し後の 見積作成には、「楽王」が活躍!
単価データには全日出版社の 「積算実務マニュアル」の情報を収録。
民間/公共工事の両方に対応し、切り替えて積算が可能です。
検索機能により目的の材料がスムーズに見つかるため、 単価の確認にも活躍します。
コストを抑えて自社仕様にフィット。「楽王3」
「 フルオーダーなら理想の仕様にできるけれど、 コストが合わない…」
「たくさん見積ソフトがあるけれど、 自社に合うものがわからない…」
「積算ルールがバラバラで、 運用の整理もしたい…」
そんなお悩みに応えるのが、セミオーダー型積算ソフト「楽王3」。
フルオーダーのような高額な コストをかけずに、自社に最適な環境を構築できます。
貴社の運用を丁寧にヒアリングし、最適なカスタマイズと運用方法をご提案します。
ソフトの導入を機に、 業務の見直しや整理を進めたい企業様にも最適です。
まずは、どんなお悩みもご相談ください!
★製品デモや資料請求はこちらから→「製品サイトお問い合わせフォーム」
★お電話でのお問い合わせはこちらから→045-451-5121045-451-5121










