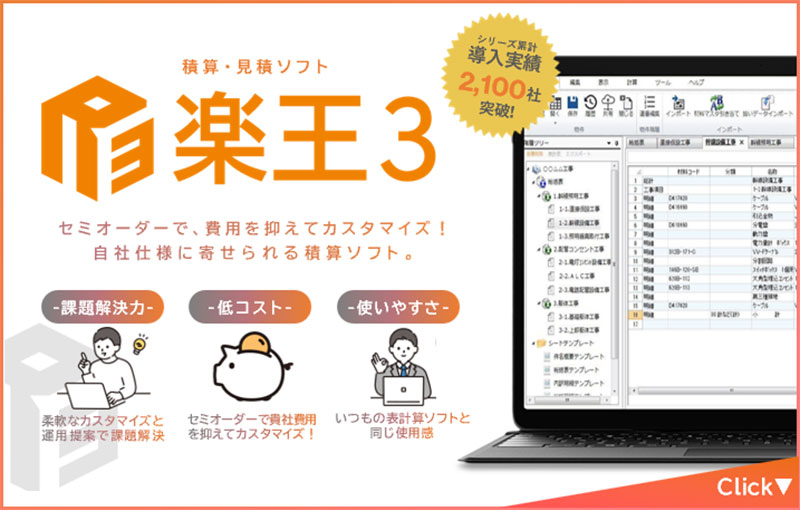こんにちは!ITの力で建設業界に貢献するアークシステムです。
近年、建設業界では、建設工事費の高騰が問題となっています。
資材はもちろん人件費も上昇し、利益確保に四苦八苦している企業は少なくないでしょう。
では、建設工事費は、実際にどのくらい高くなっており、今後はどう推移していくのでしょうか?
今回のコラムでは、近年の建設工事費の推移について解説します。
これまでの動向や今後の予想、対策についてもあわせてお伝えしますので、ぜひお役立てください。
※2025年7月時点の情報です

目次
まずは建設工事費の推移をチェック!近年の傾向は?
近年、日本の建設工事費は上昇を続けています。
「建設工事費デフレーター」は、建設工事費用の相場を示す指標の一つ。
その最新データは、2015年を基準(100)として、以下のように推移しています。
【建設工事費(建設総合)推移】
| 2011年度 | 94.7 |
| 2012年度 | 94.1 |
| 2013年度 | 96.5 |
| 2014年度 | 99.8 |
| 2015年度 | 100.0 |
| 2016年度 | 100.3 |
| 2017年度 | 102.3 |
| 2018年度 | 105.6 |
| 2019年度 | 108.0 |
| 2020年度 | 108.0 |
| 2021年度 | 113.3 |
| 2022年度(暫定) | 120.3 |
| 2023年度(暫定) | 123.4 |
| 2024年度(暫定) | 128.4 |
※国土交通省「年度次 建設工事費デフレーター(2015年基準)」より
この建設工事費デフレーターの数値からは、建設工事費が2013年以降上昇を続けており、特に近年はその上昇幅が大きくなっていることがわかります。
建設工事費高騰による影響は?
建設工事費の上昇は、以下のような影響を引き起こします。
- 建設事業者の利益率低下
- 工事価格・購入価格の上昇
- 顧客の購買意欲低下
建設工事費が上昇すると、建設事業者は価格競争に勝つため、自社の利益を削って工事価格や建物の販売価格を維持しようとします。
しかし、コストの上昇幅が大きいため、利益を削るだけでは賄えず、やがて工事価格や建設資材の購入価格にそれを転嫁せざるを得ない状況に。
そうなれば、顧客が支払わなければならない金額は高くなり、購買意欲が低下し、結果として不動産市場が落ち込む可能性があります。
建設工事費の高騰は、建設業界全体の低迷につながるおそれがあるのです。
建設工事費が高騰している理由
では、建設工事費はなぜ高騰しているのでしょうか。
建設工事費は、主に資材コストと労務コストの2種類に分けられます。
これらのコストがそれぞれ上昇していることが、近年における建設工事費高騰の原因です。
資材コストの高騰
資材コストとは、建設工事に必要な資材や機器の購入・整備に必要なコストのこと。
建設物価調査会が発表している建設資材物価指数※(2015年基準:100)によると、資材コストは以下のように上昇傾向で推移しています。
※建築費指数などと並ぶ建設資材価格の相場を示す指標の一つで、時点間や地域間での数値の変動を時系列的に観察することができる
【建設資材物価指数(都市別)】

2025年6月時点で、建設資材の相場は、2015年と比較して約40%増加しています。
資材コストが10年で4割増加していることは、近年の建設工事費の上昇に大きく影響しています。
資材コスト上昇の理由
資材価格が値上がりしている理由としては、以下のようなものが考えられます。
- 建設需要の急増
- 木材価格の高騰
- 輸送費のコスト増
- 円安
近年、世界規模で建設需要が急増しています。
需要が高まる中、新型コロナウイルス感染症の拡大やウクライナ危機の影響により、木材の受給バランスが崩れたことから木材価格は高騰し、この現象は「ウッドショック」と呼ばれるようになりました。
また、2022年以降は、エネルギー価格の上昇に加え、円安の影響も大きくなっています。
日本は主要な建築資材の原材料の多くを輸入に頼っているため、エネルギー価格と円安の影響も建築費の高騰に直結したといえます。
新型コロナウイルスの建設業への影響については、こちらのコラムでも詳しくお話ししておりますので、あわせてご参考ください。
新型コロナウイルスの建設業への影響は?今後の動きについても解説
各資材の価格高騰の理由については、以下でご紹介しています。
生コンの値上げの理由は?高騰している現状や価格状況もチェック
労務コストの上昇
労務コストの上昇も、建設工事費の上昇につながっています。
労務コストとは、人件費や社会保険料などといった、労働者の雇用に際してかかる費用のことを指します。
国土交通省によるデータによると、公共工事における設計労務単価は、2013年以降12年連続で上昇を続けてきました。
2013年度の15,175円から2024年3月には23,600円と、約55%上昇しています。
※参考:国土交通省「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」
労務コスト上昇の理由
近年の労務コストの上昇は、以下のような理由によって引き起こされています。
- 人手不足・人件費上昇
- 働き方改革の推進
- 社会保険料の上昇
建設業界は慢性的な人手不足が続いており、人材需要の高まりにつれ、人件費も上昇しています。
また、働き方改革の推進により、時間外労働に規制がかかり、工期が長期化しやすくなったことも、労務費の増加につながっています。
さらに、近年、保険加入の厳正化により社会保険加入率が上昇し、社会保険料自体も上昇傾向が顕著です。
このことも、労務コストを引き上げる要因となっています。
建設工事費は今後どう推移する?変動する物価への対応も
今後の建設工事費推移の見通しとしては、しばらく上昇または高止まりの状況が続くと考えられています。
今後数年は、大きな建設計画がまだ続くからです。
例えば、2027年にはリニア新幹線の開業予定がありますし、高度経済成長期に建てられた建物の老朽化対策、大地震に備えた耐震施工など、堅調な需要があります。
また、人件費の高騰や働き方改革の影響も続くと考えられます。
さらに、世界情勢の影響や、原材料費、燃料費などの高騰の影響もしばらく続くと予想されるため、すぐに建設工事費が下がることは考えにくいでしょう。
建設工事費高騰への対策

高騰する建設工事費を下げ、負担を軽減するためには、以下のような対策が有効です。
- 仕入れルート・施工方法の最適化
- ITシステムの導入
仕入れルートや施工方法の最適化は、コストカットにつながります。
仕入れに関しては、必要以上に仲介業者を挟まないルートを開拓し、支払う金額を下げましょう。
また、施工についても最適な方法を選択することが大切。
この点については発注者との協議も必要ですが、施工に関して常にコストカットの意識を持つことは重要でしょう。
受注側が、発注者へ品質とコストの両方を意識した提案をすることをVE提案と言います。
VE提案について「建設におけるVE提案を解説!導入効果や資格、事例までを詳しく」で詳しくご紹介しておりますので、あわせてご参考ください。
また、ITシステムの導入も、業務効率化につながります。
例えば、工事費の見積を算出する積算業務では、日々変動する物価を適切に反映していくことが重要です。
必要な材料の相場を逐一調べて反映していくのはとても手間のかかる作業ですが、積算見積ソフトを導入することで、業務効率を格段にアップさせることができます。
業務の一部自動化によって業務が効率化できれば、人件費を抑えることも可能です。
経営正常化のための対策については、以下もチェックしてみてください。
建設工事費の推移を知ろう!今後も高止まりの予想
建設工事費は近年、上昇が続いています。
建設需要増によるウッドショック、世界的な原油高騰による輸送費の高騰、円安などは資材コストを上昇させ、また人手不足に伴う人件費の高騰や働き方改革の推進、社会保険料の上昇は労務コストを大きく引き上げることとなりました。
今後も堅調な建築需要に加え、人件費や工事資材価格が下がることはないと見込まれるため、建設工事費はしばらくは上昇、もしくは高止まりの状況が続くと予想されます。
建設事業者が建設工事費の高騰に対応するためには、最適な仕入れルートの構築や施工方法の選択によって、無駄なコストを抑えることが重要です。
また、ITシステムの導入による業務効率化も推進すると良いでしょう。
月額¥3,800-から始められる!積算ソフト「楽王シリーズ」
アークシステムは、ITツールを通して、建設業に携わる方の業務をサポート。
建設業で特に手間のかかる拾い出し・積算見積をサポートする「楽王シリーズ」を提供しています。
月額¥3,800!クリックだけで拾い出し。「ヒロイくんⅢ」
図面の拾い出しには、月額たったの¥3,800(税込)から使える 「ヒロイくんⅢ」。
読み込んだ図面をクリックするだけの簡単操作で、簡単に拾い作業ができる製品です。
難しい拾い出し業務がシンプルに。手作業から約50%もの工数を削減 ※当社調べ
安価な月額制で始めやすくて、続けやすいヒロイくんを是非お試しください!
月額制で始めやすく、続けやすい。「楽王Link/Crew」
拾い出し後の見積作成には、「楽王」が活躍します!
単価データには全日出版社の「積算実務マニュアル」の情報を収録。
民間/公共工事の両方に対応し、切り替えて積算が可能です。
検索機能により目的の材料がスムーズに見つかるため、単価の確認にも活躍します。
コストを抑えて自社仕様にフィット。「楽王3」
「 フルオーダーなら理想の仕様にできるけれど、 コストが合わない…」
「たくさん見積ソフトがあるけれど、 自社に合うものがわからない…」
「積算ルールがバラバラで、 運用の整理もしたい…」
そんなお悩みに応えるのが、セミオーダー型積算ソフト「楽王3」。
フルオーダーのような高額なコストをかけずに、自社に最適な環境を構築できます。
貴社の運用を丁寧にヒアリングし、最適なカスタマイズと運用方法をご提案します。
ソフトの導入を機に、業務の見直しや整理を進めたい企業様にも最適です。
まずは、どんなお悩みもご相談ください!
★製品デモや資料請求はこちらから→「製品サイトお問い合わせフォーム」
★お電話でのお問い合わせはこちらから→045-451-5121045-451-5121